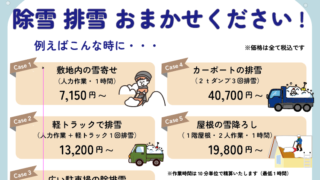そういえば、
ブログのタイトルは
雪国もいいよねって、
明るく前向きに生きようと(笑)、つけたものでした。
今年の雪は流石にへこたれましたが、
やられっぱなしではいられません!
というわけで、
ちょうど休みの日が晴天だったので、
思い立って、今年(去年も)出来てなかったスノーシューをしてきました。
スノーシューって?

この時期の雪山は、長靴で行こうものなら、
ズボズボ抜かって、歩くのが大変!
そこで役に立つのが、輪カン(かんじき)や、スノーシューです。
基本はどちらも、接地(雪)面積を増やして、浮力を得るためのもの。
軽量で小回りの効く輪カンより、
大きく浮力の働くスノーシューの方が、より深い雪に対応出来ます。
スキーとスノーボードの関係に近いですね。
この時の気温8度。
こんな硬めの雪なら輪カンでも良いのですが、
スノーハイクの醍醐味はふかふかの新雪!
新雪のときはスノーシューがおすすめです。
かやの茶屋

今回来たのは萱野高原。
青森の人は「かやの茶屋」って言います。
1杯飲めば、3年長生き
2杯飲めば、6年長生き
3杯飲めば、死ぬまで生きる
という、ミラクルなお茶が飲み放題で、
青森市民に長く愛されています。
時々ロードバイクで登ってくるのですが、
木々に囲まれた坂道を登りきると、
ぐわっと視界が広がり、草原と八甲田山が一面に。
それがこの景色なのですが、
今回はいつもよりも少し高い(5mくらい)雪の上から。
青空と八甲田山と雪原のパノラマが本当に美しい日でした。

ロープウェーの山頂駅もよく見えます。
樹氷もまだまだ見頃みたいですよ。
ヤドリギの実

寄生植物であるヤドリギの実。
色彩の少ないこの冬景色で、ひときわ目立ちます。
この冬の時期に実が残っているという事は、、、
そうです。毒があるんです。
美味しくないから残るんですよね。
ただ、この身を好んで食べる鳥もいます。
そして、ヤドリギの実はねっぱります。
(津軽弁でねばねばくっつくこと)
木に寄生したいヤドリギは、
鳥に実を食べさせて、ねっぱるウンチを出させたい。
そしてそれを枝にくっつけたい。
そうなると、葉のある時期にウンチされてもダメなんですね。
葉にくっついても秋に落葉して落ちてしまう。
冬になってすっかり葉が無くなってから、
満を持して、食べてウンチにしてもらうのが理想です。
そのためには、秋に真っ赤になって、
美味しかったら駄目なんです。
すぐに食べられてしまうので。
そんなしたたかな計算で毒を宿すヤドリギ。
西洋では昔から特別な力があるとされていて、
クリスマスにはヤドリギの枝を吊るす風習があります。
日本でも、万葉集で詠まれたりもしています。
寄生!気持ち悪い!ではなく、
古来より愛される、なんとも不思議な木。
冬の森の植物たち

どんぐりの帽子だけ残っていました。

不思議な枯れ木。
どうしてこういう形になったのか不明です。

青空に雪のようにきれいな蕾

これも寄生植物、グルグル巻き。

どこからどう見ても、
美人なプロポーションのダケカンバ。
白樺はもっと白く、もっとスラっと伸びます。
ただ、標高の限界があり、ある程度標高が上がると、
岳樺(ダケカンバ)が増えてきます。
ダケカンバの樹皮はよく燃えるので、
雪山で遭難した時は、木の根元で、樹皮を燃やして助けを待ちましょう。
うさぎの足跡も見れたり、
冬の雪原は、
普段の季節では見られない植物たちの表情が見れる、特別な場所です。
ひょうたん茶屋の薪ストーブ

かやの茶屋の奥の茶店(酸ヶ湯で運営していたところ)は、
現在、ひょうたん茶屋というお店になっています。
薪ストーブの優しい暖かさにひたりながら、
コーヒーが飲めます。
実は、この薪ストーブ、20年近く前に、
鉄工房アールさんに依頼して作ったもの。
実家を設計した際に設置して、
震災の時も大活躍だったのですが、
(暖かいし、明るいし、お湯も沸かせる)
寒がりの父が、大きな薪ストーブに買い替えたので、
お役ごめんになったのです。
ちょうど、ひょうたんさんの話を聞いて、
寄贈させていただきました。
この時期は、八甲田のスキー客が多いですので、
末永くお客さんを暖めてあげて欲しいと願っています。
そんな、想い出の薪ストーブ、
当時、ブログ書いたっけ・・・
って探してみると、有りました!
ブログ1号(gooブログ)。なんか文章が恥ずかしい。
薪ストーブ
ブログ2号(じゅげむブログ)。文字多い。
局所暖房のススメ
ちなみに今のブログは4号です。
ずっと続けてたら、結構なボリュームになってたのに・・・
長くなりましたが、一言でまとめると、
スノーシューも萱野茶屋も最高でした!